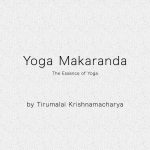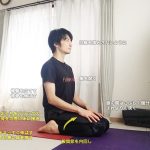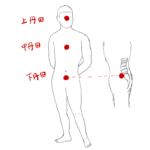ヨーガやアーユルヴェーで使われている用語は、元々ほとんどがサンスクリット語です。
このページでは、サンスクリット語の基礎知識・発音・文字などについてまとめておきます。
サンスクリット語の概要
サンスクリット語は古代インドなどで用いられていた言葉で、仏典などの多くがサンスクリット語かパーリ語で書かれています。
日本では「梵語」と表記され、現在の仏教で用いられているお経なども、サンスクリット語から中国語を経て日本語に訳されたものが多いです。
「禅」という言葉は、ヨーガでいう瞑想あるいは集中の絶え間ない連続である「ディヤーナ」が、中国で「禅那」に音訳され、それが元になってうまれた名称であると言われています。
現在のインドでは公用語はヒンディー語、準公用語が英語で、サンスクリット語を母語としている人々もごく少数いるようですが、日常的に使われているかは疑問であるとされています。
ヨーガやアーユルヴェーダのベースとなったヴェーダで用いられていたヴェーダ語がサンクリットの元になったと言われ、古典サンスクリットとヴェーダ語は共通する部分が多いですが、異なる部分もあるようです。
サンスクリット語の発音
ヨガのポーズや呼吸法は、馴染みのないサンスクリット語をカタカナで書いたものが多いので、発音したり覚えたりするのに苦労するヨガインストラクターの方も多いかと思います。
カタカナでは正確に表せない発音も多くあるので、本当の表記を知りたい方は、アルファベットかデーヴァナーガリーを用いると良いでしょう。
たとえば「ア」と「アー」は別の意味を持ち、ヨガポーズを意味する「アーサナ」も日本では「アーサナ」と「アサナ」の両方の表記が見られますが、これらも厳密には統一したほうがいいのではと主張する人々もいるのもわかります。
「o」は伸ばす音「オー」しかないので、「ヨガ」ではなく「ヨーガ」が正しいというのは比較的よく耳にする知識かもしれません。
サンスクリット語の母音
母音については、以下のようなポイントがあります。
- 「a」「i」「u」は短く切る発音(短母音)で、「ā」「ī」「ū」は伸ばす発音(長母音)である。
- 「o」と「e」は伸ばす発音(長母音)しかない。
マントラを歌のように唱えていくと、節の最後の母音は伸ばしたくなりますが、アとアーは別の意味になってしまうので、短く切るところは切って発音する必要があります。
ちなみに上記のルールから、本来は「ヨガ」ではなく「ヨーガ」と発音する、という話になります。
サンスクリット語の子音
子音については、以下のようなポイントがあります。
- 「v」は「w」に近い発音をする。
- 「s」は歯音(サ行の発音に近い)、「ṣ」は反舌音(ラを発音するような舌の形でサ行の発音)、「ś」は口蓋音(シャ行の発音に近い)で、それぞれ発音は異なる。
- 「dh」「kh」は帯気(有気)破裂音で、ため息のような息を出しながら発音する。
- 「ṇa」はラというようなつもりで「ナ」と発音する反舌音。
- 「ṅ」は[ŋ]ngの音、軟口蓋鼻音。
- 「ñ」はニャのような発音になる硬口蓋鼻音。
sの音の区別は特に難しいですが、dhやkhはそれほど難しくなく、そのあたりから気をつけるようにしていくとサンスクリット語っぽい発音になっていくので練習してみると良いでしょう。
「ṃ」と「ḥ」
ṃは日本語の「ン」とほぼ同じ。ḥは基本的に直前の母音の口の形のままで息を狭める発音で、iḥなら「イヒ」(ヒは息を出すだけのような発音)になります。
サンスクリット語の文字
サンスクリットは、ひとつの決まった文字を持たず、様々な文字で記述されたり、知識の種類によっては口伝のみで伝えられたりしてきました。
最も用いられてきた文字は、デーヴァナーガリーを始めとしたブラーフミー文字です。
日本では、主に悉曇文字が用いられています。お墓の塔婆などに書かれていることが多い文字です。日本は悉曇文字のことを「梵字」と呼んでいます。
デーヴァナーガリー
ハングル文字などと同じ「表音文字」で、各パーツが音を表し、それらを組み合わせて文字を成します。
各文字がシローレーカーと呼ばれる上部の横線でつながっていることが多いのが特徴(横線がない文字もある)。この線は、書き順としては最後に書きます。
「デーヴァナーガリー」という言葉自体は、デーヴァ「神」ナーガリー「都市」という意味で、「神聖なる都市文字」として用いられたといわれます。
悉曇文字(梵字)
「悉曇」はサンスクリット語の「siddhaṃ シッダ」を音訳した言葉で、「成就」「霊能」などの意味がある言葉です。
ちなみに「シッダーサナ」は「達人座」などと呼ばれ、ハタヨーガでは最上の坐法の一つとされています。
サンスクリット語の数
「三角のポーズ(トリコーナーサナ)」「四点で支える杖のポーズ(チャトランガダンダーサナ)」「一本足の〜のポーズ(エーカパーダ〜アーサナ)」「八支則(アシュタンガ)」のように、アーサナ名などで数が出てくることが多くあるので、1〜10までだけでも知っておくと役立つかもしれません。
1 एकम् ekam エーカム
2 द्वे dve ドヴェー
3 त्रीणि trīṇi トリーニ
4 चत्वारि catvāri チャトヴァーリ
5 पञ्च pañca パンチャ
6 षट् ṣaṭ シャト
7 सप्त sapta サプタ
8 अष्टौ aṣṭau アシュトゥ
9 नव nava ナヴァ
10 दश daśa ダシャ