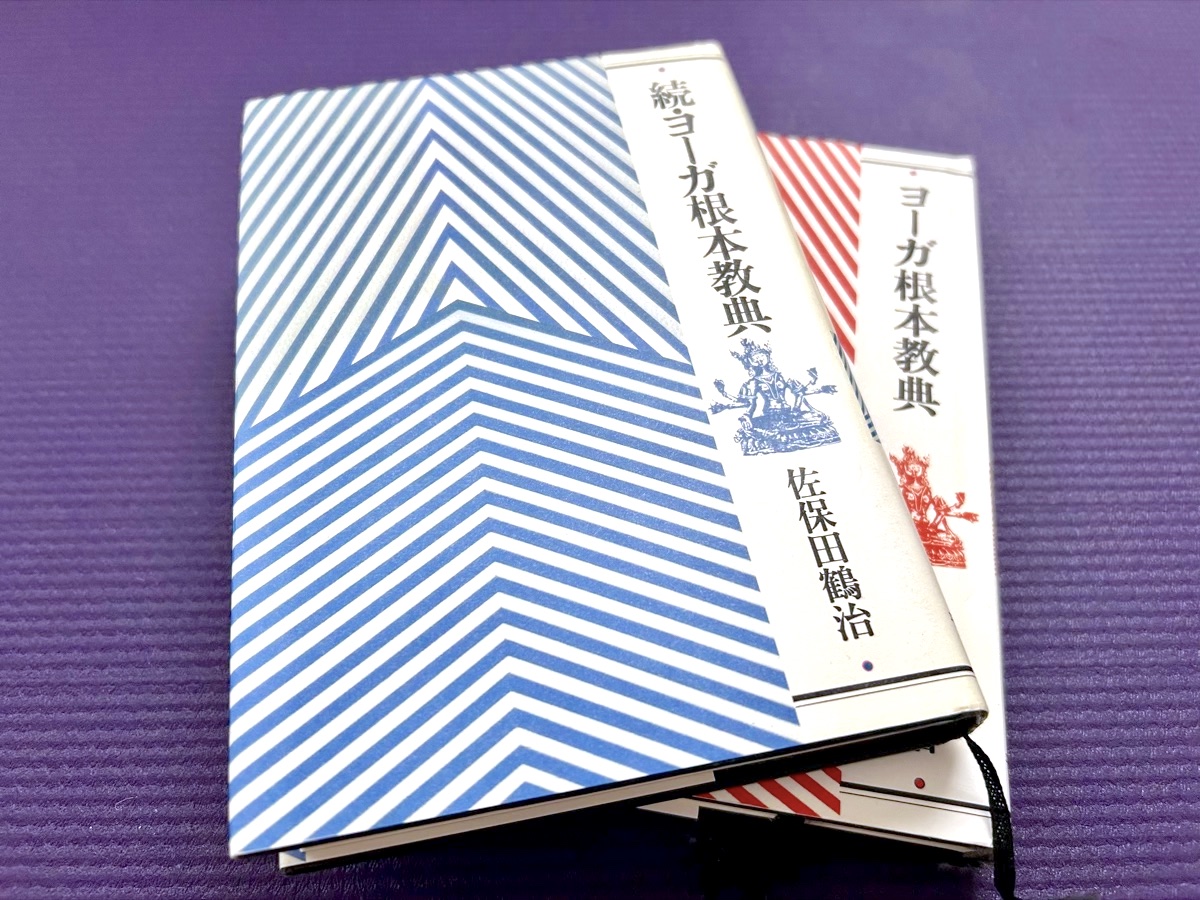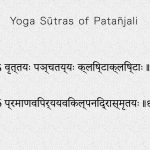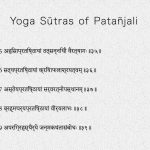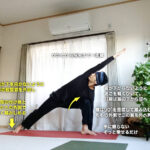現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。
今回は第1章の後半、真我(アートマン)と世界に関する部分を読んでいきます。
用語辞典:アートマン
この記事の目次
真我(アートマン)
このあたりで訳者によって節の数え方が異なってきますので、少し煩雑ですが並べて表記していきます。
佐保田訳1.51節(マリンソン訳1.50節・ヴァス訳1.49節)「万物は宇宙意識から生じた。これらの全てを放棄して、宇宙意識へ帰依すべし。」
世界は「私」の感覚によって生まれているとしたら、この宇宙意識こそが「私」であるということになります。
この世界は全て「苦」であるという話は先に出てきましたが、苦である世界が滅することで絶対的「空」が生ずるため、アートマンはすなわち「楽」であると説明されています。これもヨーガの考え方でよく出てきますが、もともとは「楽(至福・アーナンダ)」であったが様々な経験をするために「苦」の世界を作ったというように考えられています。「空」の概念は、仏教における主要な考え方であり、シヴァサンヒターにはヨーガスートラなどと同様に様々な宗教の考え方を統合していく姿勢が見られます。
訳者によって主体となる意識の解釈が異なるので◯◯としていますが、佐保田訳1.72節(マリンソン訳1.71節・ヴァス訳1.70節)「◯◯が意欲することによって万物が生まれ、その意志から無明が生まれるため、万物は本来幻である。」と説明されており、その主体の解釈を佐保田氏は「プルシャ(真我)」、ヴァス氏は「The Load(主)」つまりプルシャと同一のブラフマン、マリンソン氏は「man(人)」と訳しています。
結局のところそれらは同一であると理解していれば良いかと思いますが、微妙に解釈が異なるところも気にしていく必要があるかもしれません。
ヨーガとマーヤー
この世界は全て自分自身が作り出した幻(マーヤー)である、ということに気づけば、この世界には永遠の至福が無いことを悟ります。自分の作り出した世界で、いろいろな経験をした上でそれを悟り、本来の真我へ戻っていくということになります。(それに意味があるのか、それとも意味は無く全ては戯れなのか、ということはここでは詳しく触れられていませんが、探究の余地のあることです。)
佐保田訳1.65節(マリンソン訳1.64節・ヴァス訳1.63節)の「アートマンによって、アートマンの内に永遠の至福を観た時、世界を忘れ、サマーディ(三昧)の境地を強く感じることができる。」、佐保田訳1.67節(マリンソン訳1.66節・ヴァス訳1.65節)の「万物が幻(マーヤー)に過ぎないと知ったならば、肉体や富や快楽から成る喜びの対象は無い。」といった境地に至るのが、ここでいう智慧部門・ジュニャーナヨーガの目的ということになります。
サマーディ(三昧)はハタヨーガやラージャヨーガのゴールでもあり、共通する境地に達することになります。
世界の始まりと終わり
物質世界が「五大元素(虚空・風・火・水・土)」によって成り立っているというのは、ヨーガの原理としてよく用いられますが、ここでも五大が説明の中に用いられており、アートマン(真我)は五大の中に遍在しているが、それらとは混合しないと説明されています。また、時間と空間といった概念も五大が作り出しているもので、アートマンはそれとは別のものであり時間や空間に縛られることなく、永遠不滅であるといいます。
佐保田訳1.75節(マリンソン訳1.74節・ヴァス訳1.73節)「虚空から風が生じ、風から火、火から水、水から地が出現した。以上が創造の仕組みである。」というように、五大元素の出現と世界の創造が説明されています。
マリンソン氏は虚空を「air」と訳し、ヴァス氏はサンスクリット語そのままで「akasa アーカーシャ」を用いています。「虚空」という概念は、スカスカな「空」というよりも、ぎっしりと元素が埋め尽くした空間というようなイメージに近いもので、それを現代では「エーテル」と呼ぶこともあります。
佐保田氏は最後の文に「実在(梵・ブラフマン)の上に成り立った創造の仕組みである」という文言を加えて、それらが実在ではなく幻であるということを強調しています。
佐保田訳1.81節(マリンソン訳1.81節・ヴァス訳1.78節)「大地は微細に分解して水に溶け、水は火の中に消え、火は風の中に消え、風は虚空の中に消える。偉大なる虚空は無明の中に消え去り、無明は至高なるブラフマンの住まいへと消え去る。」といったように、世界の終わりについて述べられています。
このように、全ては「真我ではないものを『私』と認識する」という「無明」から生じていて、無明がなくなれば世界も役割を終えて消滅すると説明されます。
無明というのはすなわち「分離の思考」のように思えます。この物質世界は分離の極致であり、なにを伝えるにも不自由です。その不自由な世界でこそ、いろいろな経験ができるということになります。2人以上の人がいなければ、戦うことも愛し合うこともできません。
ここで言う世界の終わりというのは、恐ろしい破滅的なものではなく、色々な経験の末に悟りに至り、役目を終えた世界(自分の作り出した世界)が消えて、元のところへ戻っていくというようなイメージです。
人間と業(カルマ)
佐保田訳1.93節(マリンソン訳1.93節・ヴァス訳1.89節)「人間は父のアーナンダマヤコーシャ(物質的な身体)から、前世の業によって生まれる。賢者たちはこの美しい肉体を、前世の業の果報を受けるためのもので、苦であると見なしている。」と示されており、肉体を得てこの世界に生まれてくるのは、過去の行為の結果であるとしています。目的とするところは、様々な経験を経た末に輪廻から脱することなので、素晴らしい肉体を得たとしても、それは苦を味わうためのものということになります。
コーシャ(身体・鞘)については以下用語辞典なども参考にしてください。
用語辞典:コーシャ koṣa
ここで「梵卵」という言葉が出てきますが、これは宇宙そのものや肉体自身を表すためにも使われている言葉のようで、苦楽を経験するために五大元素を集めて作られたものであるとされます。
佐保田訳1.97節「五つの元素の結合から生じた無数の粗大な物がらが梵卵(宇宙)のなかに群れをなすところで、その物がらの内にジーヴァ(個人霊)は諸業を引き具して存在するのである。」
また、ここで「ジーヴァ(個人霊)」と称する概念が出てきます。神智学などでもモナド(分霊魂)という言葉が出てきます。元々唯一のブラフマンの意識から、「個人」「私」を認識するための分割された意識が作られ、それが個別意識となり、全ては一つだったことを忘れて、他の人間とは別の存在であるという認識を生むことになります。
佐保田訳1.99節(マリンソン訳1.99節前半・ヴァス訳1.95節)「すべての存在のうちに住むもの(ジーヴァ)は非物質であるが、物質の内に住むことによって業の果実を味わう。そして、ジーヴァと呼ばれるものは自己の業に縛られて、物質に基づいて種々のものになるのである。」とジーヴァについて説明されています。
ジーヴァは物質の中にありつつ非物質であり、物質の内に住んでいる、まさに一般的に「霊」と考えられている概念と近いものです。そして、それは人間や生物だけでなく、あらゆるものの中にあるといいます。私もこれに関しては同じような感覚があり、原子のような微細なものでさえも、輪郭を持つ全てのものには「隣のものと自分は別である」という個別意識があるのだと思います。その意識がなくなったとき、輪郭は溶けて周りに同化していきます。
第1章の最後は、佐保田訳1.100節(マリンソン訳1.99節後半・ヴァス訳1.96節)「梵卵(宇宙)の中で、業の果報を刈り取るためにジーヴァは繰り返し生まれる。業の果報が尽きたとき、至上のブラフマンの中へ消える。」といった感じで締められていますが、3者の訳は微妙に異なるので、少し組み合わせてみました。
また、マリンソン訳では最後に「こうして、主とパールヴァティーとの対話の形でヨガを論じた、栄光に満ちたシヴァサンヒターの第一章は幕を閉じる。」という一節が加えられています。
第2章は、人間の構造などについてより詳しく語られ、ようやくチャクラやナディといったハタヨーガらしい話も出てきます。
前記事:シヴァサンヒター概説【2】1.20-1.50 カルマとジュニャーナ