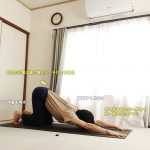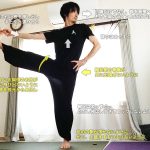梵:योग yoga
英:connection, junction, accession, union, total, self-concentration…
日:繋ぐ、結ぶ、統御する、達成する
ヨガ(ヨーガ)の意味
ヨガ(ヨーガ)とは、馬車の手綱をつなぐ「くびき」を意味するyuj(ユジュ)に関連する言葉。
「心の統御が成った状態」をヨガ(ヨーガ)と言う場合もあり、「心の統御を成すための行」をヨガ(ヨーガ)と言う場合もあり、解釈の広い言葉である。その真の意味は、文脈から注意深く判断する必要がある。
「ヨガ」と「ヨーガ」のカタカナ表記について
日本では「ヨガ」と表記されることが多いが、サンスクリット語のoは必ず長母音となり「オー」と読むため、発音に忠実に表記するのであれば「ヨーガ」となる。
「ヨーガ」の起源
ヨーガの起源については、はっきりと分かっていない部分が多い。
紀元前2500年-1800年頃のインダス文明の印章の中にヨーガの坐法に似たものがあったことから、そのあたりをヨーガの起源とする説が多いが、それも推測の域を出ない。
「ヨーガ」という言葉が現れたのは、現在判明している最も古い時期のものでは、紀元前500年-紀元前400年の「古ウパニシャッド初期」に成立した「タイッティリーヤ・ウパニシャッド」であると言われる。ただし、そこでヨーガという言葉がどのような意味であるかは明確には分からない。
同時期に成立したと言われる「カタ・ウパニシャッド」では、身体を馬車に例えて統御する道を示している。そこでは「ヨーガ」という言葉は用いられていはいないが、くびきをかける「ユジュ Yju」という言葉が用いられている。感官は馬であり、身体は馬車であり、それらをコントロールする御者がアートマン(真我)であるとしていて、その過程は後世のヨーガにつながるものであるとする説がある。
カタ・ウパニシャッドなどと同時代に成立したと思われる「シュヴェーターシュヴァラ・ウパニシャッド」では、より具体的にヨーガの道が示されている。そこにはすでに坐法・姿勢(アーサナ)や制感(プラティヤーハーラ)や調息法(プラーナーヤーマ)に通じるものが含まれている。
ヨーガスートラにおけるヨーガ
ヨーガスートラにおいては、ヨーガとは「心の働きを止滅することである」などと表現される。
そのための行法として、アシュタンガヨーガ(8支則のヨーガ)、カルマヨーガ、クリヤーヨーガなどの道が示され、それらをまとめてヨーガスートラのヨーガはラージャヨーガと呼ばれている。
ハタヨーガ
ヨーガスートラの後に現れる密教的なハタヨーガでは、ラージャヨーガに至るための階梯として、様々なアーサナ・プラーナーヤーマ・ムドラーなど体を用いた行法が実践される。
道は様々あれど、目指す境地は同じ「サマーディ(三昧)」であるとしている。
瑜伽(ゆが)
中国では、ヨーガは瑜伽(ユージャー Yújiā)と音訳されている。
真言宗や天台宗など日本の密教では、瑜伽(ゆが)という言葉が用いられる。
ただしサンスクリット語における「ユガ」は、「期間」などを表す別の言葉である。
関連記事
- ヨガの目的・基礎知識〜自分なりに、8支則をライフスタイルへ取り入れる〜
- 日本人に適したヨガ 〜正しい筋肉・深部柔軟性・陰陽バランス・洞察力〜
- 国ごとに異なる「一般的なヨガ」と「インドのハタヨガ」の比較 〜体と文化〜
- ヨガ(ハタヨガ)の種類、選び方のコツ(初心者向け)
- ヨーガスートラ(ヨガスートラ)日本語訳・原文・発音一覧
- ヨガの種類・流派一覧