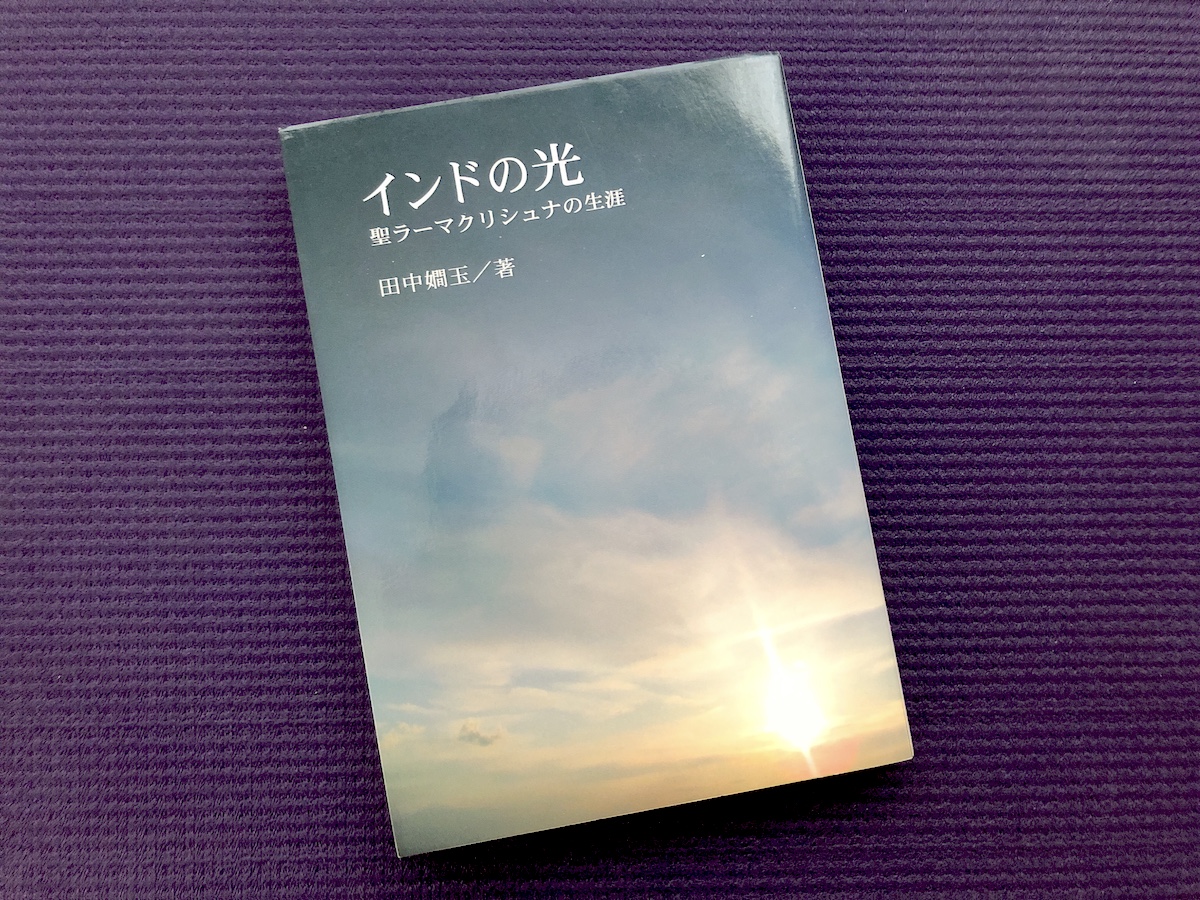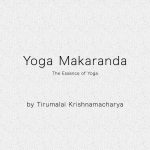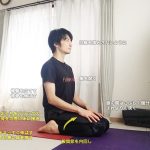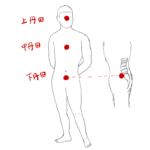セルフケアやヨーガの勉強などのために、私が読んできた書籍を紹介していきます。
今回は、「インドの光 聖ラーマクリシュナの生涯/田中嫺玉(著)」です。
この記事の目次
簡単に言うと、どんな本?
インドの聖者、ラーマクリシュナの生涯をまとめた伝記です。自伝ではなく、ベンガル語の翻訳などを長年行ってきた田中嫺玉氏による著作です。
ラーマクリシュナは1836年から1886年に生きた人物で、弟子のヴィヴェーカーナンダ氏が欧米にその教えを伝えたことで、インドの外まで広く大きな影響を及ぼしました。ガンジーや詩人タゴールなど多くの人物から讃えられ、またイスラム教やキリスト教などの人々からも聖者と讃えられた特異な存在です。
彼の生活や活動を伝える写真も残されており、この本でもラーマクリシュナ自身の姿や、住居や周辺(ベンガルの田舎町)の様子、人々に教えを施す様子、サマーディに入っているときの奇妙な様子、関連する人物たちなどの写真も多く用いられ、その生き様が細かく伝えられています。
ラーマクリシュナはベンガルの田舎っぽい親しみやすい言葉を使っていたようで、それを田中嫺玉氏は噺家のような軽妙な語り口に訳すことで表現しています。また、歌として伝えることも多かったようで、それをこの本では日本語で七五調に訳していたり、彼の醸し出していた雰囲気がなるべく伝わるようにと工夫されています。
あと表紙がなんかキレイです。
どんな人にオススメ?
「ヨガ(ヨーガ)」って何なんだろう?「バクティヨーガ」って何?あるいは「宗教」って何なんだろう?といったことに興味のある方には、参考になるかもしれません。
ラーマクリシュナがヨガのポーズを練習していた様子などは全く出てきません(むしろ坐っている写真は、だいぶ姿勢が悪いです 笑)。彼は自分のイシュタ(理想神・信仰の対象)と決めた神「カーリー」を、信愛し祈るということをひたすら行っていました。このように個人の神を信愛するという道を「バクティヨーガ(信愛のヨーガ)」と分類します。
参考:ヨガの大分類(ジュニャーナ・バクティ・カルマ・ラージャ)〜体を動かすヨガ・それ以外のヨガ〜
ラーマクリシュナは聖典すらも読まず、外から得た知識を用いず、祈りを重ねた結果「ニルヴィカルパ・サマーディ」に至り、その過程で得た智慧を人々に伝えていました。様々な宗教・宗派の人々が彼のもとを訪れ、その修行者が長年かかって体得した境地へと瞬時に達し、世界中の宗教に共通する真理を伝えていたようです。
狂人とも思われるほどの集中力で、自分が信愛すると決めた神に祈り続けていた彼が、その神以外を否定することなど全く無く、世界中の宗教家と論を交わし、本など全く読まず、様々な価値観を持つ人々から聖者と讃えられるような智慧を伝えていたという事実は、「宗教」そして「知識」「智慧」というものを考え直すヒントになるかもしれません。
私個人の読んだ時期・感想
私はこの本を2017年後半に購入して読んでいたようです。2016年の年末にインドに行っていたので、2017年は年始から「ガンジー自伝」を読み始めたり、以前紹介した「ヨーガの哲学」などを読んでヨーガの歴史や哲学についてさらに深めようとしていたようでした。
いろいろな本に出てくる名前だったので、なぜ彼が多くの人に讃えられているのだろう?と気になって、調べてみようと思ったのがきっかけだったと思います。
この本が描いている地域は、インドの東の端あたりのベンガルですし150年前くらいなので、私が訪れたケララのある南インドとは文化も言葉も結構異なっていることでしょう。
それでも、寺院や田舎町の写真や、人々の生活の丁寧な描写などを読んでいると、インド独特の雰囲気に浸っているような気分になりました。
インドのアシュラムや寺院などを見ていると、本当にいろいろな宗教が独特な形で融合しながら存在しています。聖書とコーランがふつうに並んで置かれていますし、キリスト教の寺院で十字架を首にかけながらヨガをしている人もいます。
私も研究するにつれて、全てのまっとうな宗教は、同じ共通する真理につながっているという実感があったので、ラーマクリシュナの生き様はまさにそれを表しているように思えました。
また、私はいろいろな本を読んで研究していましたが、どうもやはり同じ真理を、人それぞれに適した別の表現にして伝えているのだなと思えていたので、彼は様々な智慧を人々に伝えていたのに全く本を読まなかったというのはとても納得できました。おそらく、心静かに待っていれば、必要なことは「降りてくる」のか「湧き出てくる」のか表現は色々かもしれませんが、自然と得られる(あるいはすでに持っていたと気づく)のだと思います。
そして彼はほとんど自分の部屋で、寝起きして瞑想をして、自然と訪れる人々と話をして、という生活をしていたのも親近感がありました。私もいまはほとんど家で、訪れる人々にレッスンをして、たまに出張レッスンをして、同じような感じでやっています。ヴィヴェーカーナンダのような運命的な弟子に出会える日が来るんでしょうかね、それも準備ができたら自然に、ということなのでしょう。
この本を読んでいると、インドの空気や聖者の持つ雰囲気に触れることができ、なんとなく「霊性」が高まるような、そんな感覚があります。
同様な感覚を得られた本はいくつかあって、いずれまた紹介していきますが、いままで紹介してきた中では「インテグラル・ヨーガ」や「あるがままに生きる」などです。
低い波動に出会って「霊性」が下がっているなと感じるときは、たまにこういった本を手にとって読んだりします。波動ってなんじゃい、とかが気になる人は、今連載している「クンダリニー・タントラ」を追って行ってみるとヒントになるかもしれません。
この本にも登場するマヘンドラナート・グプタ氏がラーマクリシュナの言葉をまとめた、大量の「不滅の言葉(コタムリト)」が残っており、田中嫺玉氏が日本語訳したものが出版されています。しかし数冊にわたるものすごい量の文章だったので、まだ全部読んだことはありません。そこから抜粋して小さな文庫本になったものも出ていたので、これはよく持ち歩いて読んでいました。この小さな本も十分、「霊性」の高まりを感じられるかもしれません(多分いまは絶版になっているようです。私も古本で手に入れました)。
「不滅の言葉(コタムリト)―大聖ラーマクリシュナ (中公文庫)」田中 嫺玉 (翻訳)
「インドの光 聖ラーマクリシュナの生涯」の目次
- 序章 インド精神文化の土壌―近代インド誕生の時代背景
- 第1章 神の化身の誕生―無邪気に遊び暮らした幼少年時代
- 第2章 カーリー大実母との出合い―南神寺での修行
- 第3章 さらなる高みへ―ラーマクリシュナとしての出発
- 第4章 ラーマクリシュナと身近の人びと―妻サーラダマニとの宗教的結合
- 第5章 神を求める人びととの語らい―ケーシャブ・センとの交流
- 第6章 『不滅の言葉』の輝き―弟子たちに語るブラフマンの世界
- 第7章 世界への旅立ち―愛弟子ナレンドラと普遍的福音
- 付録 ラーマクリシュナの愛唱歌
「インドの光 聖ラーマクリシュナの生涯」の購入先
Amazon
この書籍に関連する記事
- ヨガの大分類(ジュニャーナ・バクティ・カルマ・ラージャ)〜体を動かすヨガ・それ以外のヨガ〜
- バガヴァッドギーターとは 〜様々なヨーガや宗教哲学を統合した聖典〜
- ヨーガスートラ(ラージャヨーガ・アシュターンガヨーガ)における、サマーディの段階
- ヨーガの歴史をつなげる 〜ウパニシャッド、バガヴァッドギーター、ヨーガスートラ、ハタヨーガ〜
- インドの聖者の本を読む 〜ヨガナンダ、ラーマクリシュナ〜
関連書籍
「大聖ラーマクリシュナ 不滅の言葉(コタムリト) 第一巻」マヘンドラ・グプタ (著), 田中 嫺玉 (翻訳)