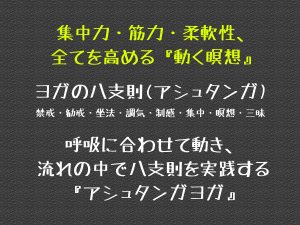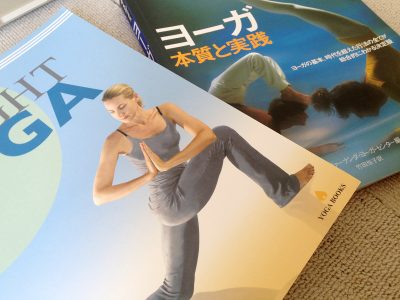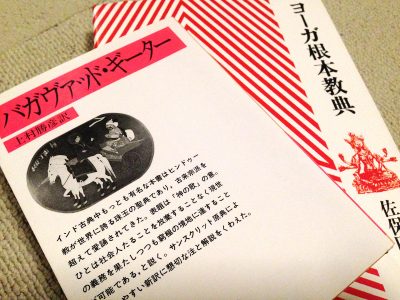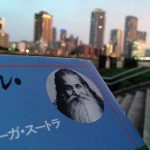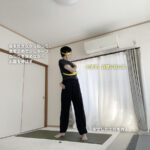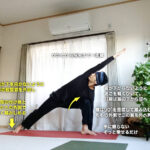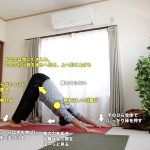「アシュタンガヨガが好きで続けているけれど、いつか怪我をしそうで不安」
「過去に怪我をしたので、正しいやり方が知りたい」
という方が、よくプライベートレッスンにいらっしゃいます。
怪我をして初めて気づくことも多いのですが、ヨガは「体」だけでなく「心」も含めて全体的に整えるものです。
大きな怪我をする前に、心と体のバランスを整えるヨガのテクニックを知っておくと良いかと思います。
この記事の目次
アシュタンガヨガでのよくある怪我のパターン
過去にいろいろな方にお聞きした中で、アシュタンガヨガのプライマリーシリーズで怪我をする人の多いポーズを挙げてみます。
- 太陽礼拝(チャトランガダンダーサナ・アップドッグ・ダウンドッグ)で慢性的に手首・腕・肩が痛くなる
- トリコーナーサナで、前側の膝を痛める
- 蓮華座で股関節・膝・足首を痛める
- ジャンプスルーを失敗して、肩・肘・手首を痛める
- ウルドゥヴァダヌラーサナ(ブリッジ)で腰や背中を痛める
- ウルドゥヴァパドマーサナで首を痛める
- チャクラーサナで首を痛める
- ヘッドスタンドで倒れて背中や足を痛める
- ヘッドスタンドからの着地で足を痛める
ひとつひとつのやり方やコツの解説は、個別の記事を参考にしてみてください。
今回は怪我をしないための、前提となる基礎知識を2つ挙げてみます。
前提1:「心のバランス」8支則を実践する
長いこと練習は続けているけれど「アシュタンガヨガ(アシュターンガ・ヨーガ)」の意味を知らないという方も多いようです。
現在一般的に日本のヨガスタジオで行われているアシュタンガヨガは、正確には「アシュタンガ・ヴィンヤサ・ヨガ」と呼ばれ、「ヴィンヤサヨガ(呼吸に合わせてポーズをつないでいくヨガ)」の中の1つの流派で、「アシュタンガ」=「ヨガの8支則」を短時間の練習によって実践するためにつくられたものです。
本来は出家したり1日の大半を修行にそそいで実践されていたアシュターンガを、通常の社会生活をしながら実践できるようにという目的でつくられたと言われます。
「アシュト」が8、「アンガ」は枝・内容などの意味です。
8支則とは、以下の8つです。
1.ヤマ 社会的規範
2.ニヤマ 個人的規範
3.アーサナ 姿勢・坐法
4.プラーナヤーマ 調気
5.プラティヤハーラ 制感
6.ダーラナ 集中
7.ディヤーナ 瞑想
8.サマーディ 三昧
いわゆるヨガポーズは第三支則の「アーサナ」にあたります。
しかしアーサナを行う前に、大切な「道徳(ヤマ・ニヤマ)」があるのですが、これを知らずにヨガをしている人も多いようです。
ヤマ・ニヤマには、ヨガを実践する上でとても重要なヒントが教えられています。
とはいえ、現代のヨガでいきなり道徳から始めようという人はとても少ないと思います。まずはポーズから、エクササイズとして始める人が多いでしょう。
なので、エクササイズとして行っていく中で、違和感を感じたり、できないポーズに出会って壁にぶつかったりしたときに、必要に応じてヤマ・ニヤマにヒントを求めていくという流れが現代社会にフィットしているのかもしれません。
ヤマ・ニヤマの中で、とくにアシュタンガヨガで怪我をしないための、重要なヒントを含むものをいくつか挙げてみます。
ヤマの最初に、まず「非暴力(アヒンサー)」があります。
これにはいろいろな解釈がありますが、自分も含めてあらゆるものにたいして苦痛を生まないようにするというように捉えると良いかと思います。
自分も、周りの人にも、先生にも、苦痛を与えないように振る舞えるようにすると良いですね。
たとえばオシャレなスタジオで素敵な人達と一緒にヨガをしていたとしても、「自分には少しポーズが難しいな」という感覚があったら、周りの人たちは気にせず、無理をしないようにしましょう。自分の感覚がとても大事ですので、それを麻痺させないように磨いていきましょう。無理に真似をしても、怪我をしてしまうかもしれません。
あとはニヤマの中の「知足(サントーシャ)」も重要です。
アシュタンガヨガは順番が決まっているので、次へ次へと進んでいきたくなってしまいがちですが、一つ一つポーズをしっかりできるようにしてから、次のポーズへ進んでいくようにするのが正しいやり方です。
今日の自分はここで十分と知って、無理をして限界を超えすぎないことです。
ただ、サボりすぎないようにベストを尽くす「熱意(タパス)」も大事でしょう。
新しいポーズを学びたい・次へ進みたいという心と、今の自分を正確に把握して留まる心、バランスを取りながら進んでいくようにしましょう。
前提2:「体のバランス」柔軟性・筋力・体力を偏りなく高める
関節を曲げるには、片方の筋肉を縮め・逆側の筋肉を伸ばします。
この両側の筋力や意識が偏った状態で、柔軟性だけを高めようとすると怪我をします。
あるいは、そもそも体を支える筋力がない状態で、ブリッジのように重力に逆らうようなポーズを行ったり、ヘッドスタンドにピョーンと跳んでトライしようとしたりすると、バランスを崩して倒れて怪我をします。
ヨガではとくに、普段あまり使わない側、表側より裏側、外側より内側(インナーマッスル)を正しく使うことで、よりバランスの取れた体の使い方ができるようになっていきます。
そして、安全に戻ってくるまで体を支えられる体力も必要です。ヘッドスタンドに耐えられても、最後に戻ってくる時にバターン!と着地して足を怪我することもあります。
とくにアシュタンガヨガは終盤にブリッジやヘッドスタンドがあるので、そこで万全の態勢で臨むためには十分な体力が必要です。
そのために、ポーズ間に入るヴィンヤサ(ハーフヴィンヤサ・太陽礼拝の後半の動き)を行う回数をだんだん増やしていくのが有効です。
ハーフプライマリーの後半は、坐位の柔軟ポーズが主になるので、これだけ連続して行っていると結構楽ではありますが、前屈と股関節の柔軟性だけに偏った練習になってしまいます。
筋力と体力を合わせて身に付けていくために、ハーフヴィンヤサはとても有効です。前屈ポーズが続く中にアップドッグという後屈が入ることも、重要なバランスをもたらしてくれます。
周りに影響されすぎず、自分のバランスを見つけながら進んでいく
アシュタンガヨガにハマる理由として、「アシュタンガヨガをやっている人たちがカッコイイ(体が美しい・ストイックな雰囲気など)」というのが結構多いように思えます。
そういった人たちと一緒にレッスンをするのは、刺激を受けていつも以上にがんばれたり、ヒントを得られたりすることもありますが、必要以上に自分もキレイに見せよう&早く出来るようになろうと無理をしてしまうこともあります。
そういった雑念によって自分を見失わず、バランスを取りながら、進んでいきましょう。
虚栄心、余計な心の働きを抑えて、今の自分に最適なペースを見つけながら練習をしてみてください。
アシュタンガヨガだけをひたすら練習している人も多いですが、たまには別のヨガをやってみたり、ヴィンヤサヨガとして実践する以外にもアーサナひとつひとつに時間をかけて向き合ったり、個別の筋肉のトレーニングやストレッチに意識を向けてみるのも良いかもしれません。自分の癖に気づき、バランスを崩していた部分が見つかるということもあるかと思います。