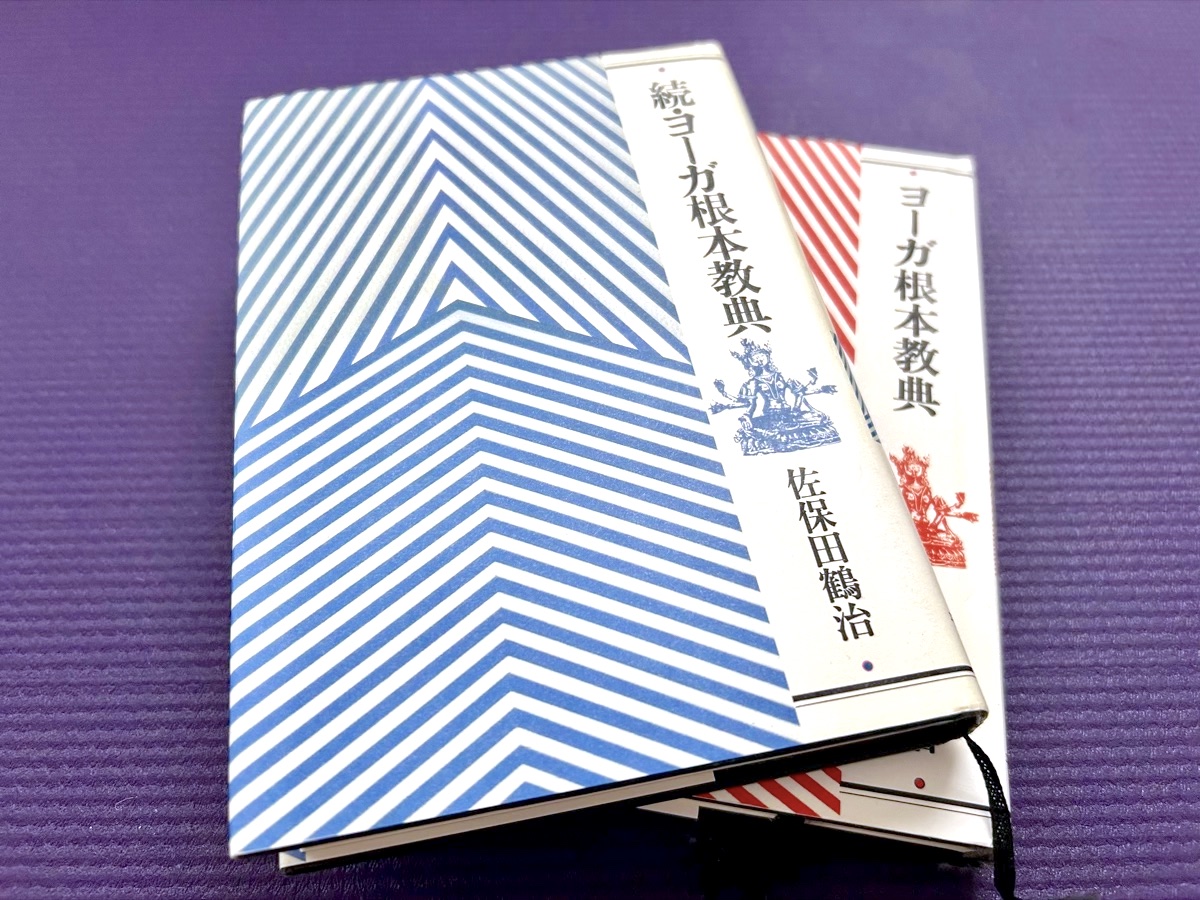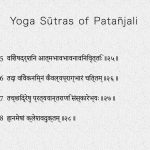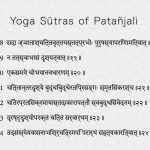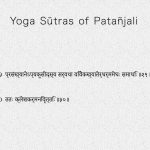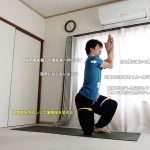現存するハタヨーガの三大教典のひとつ、シヴァサンヒターの概説です。
今回は第3章の、ヨーガ修行の4段階(アーランバ・ガタ・パリチャヤ・ニシュパティ)に関する部分を読んでいきます。
以下引用部分は基本的に以下書籍の佐保田鶴治氏の訳を用い、必要に応じてヴァス氏・マリンソン氏の訳と比較しながら進めていきます。
アーランバ段階
基本の調気法である片鼻呼吸法を、日々規則正しく実践すべしという前記事までの流れの後、ヨーガの修行の4段階についての説明が始まります。
それぞれの段階において、調気が進んで気が整っていくにつれて起こることが説明され、また次の段階に進むまでに行う行法が示されています。
まず、第一のアーランバ段階です。
アーランバ段階で起こること
3.48節「〔アーランバ段階〕調気の最初の段階においては、行者の体が汗ばみ始める。汗が出たならば、それを体に塗りつけるべし。さもないと、身体のなかの根本成分が無くなる。」
3.49節「調気の第二の段階においては、戦慄(ふるえ)が起こり、次の段階では蛙のように飛び歩くと説かれている。さらに修習が増強されると、空中歩行ができるようになる。」
3.63-64節「ヨーギーは次の如きシッディが得られる─予言能力、思いのままに移動する能力、遠隔透視能力(千里眼)、遠隔透聴能力、微視能力、他身に入る能力、大小便で磨いて劣等な金属を黄金に変える能力、事物を見えなくする能力。」
細かいところも気になりますが、ひとまず今回は概説ということで、ざっくり見ていきましょう。
調気の行が進むにつれて、様々な現象や能力の目覚めなどが起こると説明されています。
空中歩行ができるようになるまでは、前記事で示された勧戒を守るべしと指示され、さらに調気が進んでカパ・ピッタ・アニラ(ヴァータ)のドーシャの乱れがなくなったときは、食事に関する勧戒は破ってもよいなどと指示されています。ドーシャはアーユルヴェーダでも用いられる3つの要素で、そのバランスによって体や心の性質が変わるとされ、食べ物や行動や思考によってドーシャバランスは変化していきます。
アーランバ段階における行法
アーランバ段階に至った後の具体的な行法としては、3.57節で「長い間聖音オームを低声に誦すべし」、3.59節で「十六の調気行によって前生で得たところのさまざまな福業と罪業を滅ぼすことができる」などと示されています。16の調気法はここでは具体的に示されていません。
また、ここから各段階において、「どのくらいの間クンバカをできるようになるか」が示されていきます。息を止めていられる時間が、気の整い度合いに関わっているということになります。
アーランバ段階の最後では、「3ガティカ」のクンバカができるようになり、前述の3.63-64節に並べられたシッディ(超能力・霊能)が全て得られると説明されています。
ガティカという単位は、文脈によって解釈が異なるようですが、60ガティカが1日とする考え方によれば、1ガティカは24分、3ガティカは72分ということになります。マリンソン氏も72分、佐保田氏は約1時間半と注釈を加えています。
72分間息を止める……と解釈するのか、72分の基本の調気行を行うと解釈するか、あるいはガティカを別の時間単位と解釈するか、難しいところです。ちなみに純酸素を使わない息止めの現在のギネス世界記録は11分35秒だそうです。しかし地中に埋められて長期間生きていられるヨーガの技法を使う人々にとっては、72分というのは現実的な数字なのかもしれません。
ガタ段階
ガタ段階で起こること
3.65節「〔ガタ段階〕調気の修行中に、より高級な段階であるガタの境地が現れたならば、この輪廻のなかで成就し得ないことは一つも無い。」
3.66節「ガタというのは、プラーナ気とアパーナ気、ナーダとビンドゥ、ジーヴァ・アートマンとパラマ・アートマンとが出会って合一することから出た名称である。」
ガタというのはもともと瓶(かめ)の意味で、ゲーランダサンヒターのヨーガが「ガタ・ヨーガ」と呼ばれていたように、「ヨーガの火によって焼きを入れる」ことで肉体が浄化されて容易に崩れなくなる、という意味合いがあると佐保田氏は注釈を加えています。
参考:ゲーランダサンヒター概説1.1-1.11 〜ヨーガの目的、サプターンガ・ヨーガ〜
また、ガタ段階においては「プラーナとアパーナ」「ナーダとビンドゥ」「ジーヴァ・アートマンとパラマ・アートマン」が合一していると説明されています。
プラーナとアパーナの合一については、ハタヨーガの行法として下腹部に気を集める技としても行われています。
ナーダは心臓のチャクラから発せられる音で、ビンドゥは後頭部の一番上の部分や、そこから滴る雫などを表します。佐保田氏の解釈では、ナーダはオームの音に関係しており、最後の「ム〜」の音が終わる瞬間がビンドゥである、と説明されています。だからどうなのか?という詳しい説明はここではされていません。
少し考察してみるとすると、頭のビンドゥと心臓のナーダの間の位置にある、ヴィシュッディチャクラも関係しているようにも思えます。クンダリニータントラでは、ビンドゥから滴り落ちる甘露(ネクター・アムリタ)を喉のヴィシュッディが解毒すると説明されています。
参考:「クンダリニー・タントラ」を読む【35】第2章 8節:ヴィシュッディチャクラの位置や特徴
ジーヴァ・アートマンとパラマ・アートマンの合一は、ヨーガスートラやハタヨーガプラディピカーで示されているゴールと同じです。
参考:ハタヨーガプラディーピカー概説 4.1-4.34 〜ヨーガが成った状態を表す、様々な表現〜
ガタ段階における行法
ガタ段階においても引き続き、クンバカ(止息)を長くしていくことについて説明されています。
3.67節「一ヤーマ(三時間)のあいだイキを止めることができると、間違いなくプラティアーハーラ状態が生ずる。」
クンバカの長さは1ヤーマまたは8ダンダと書かれていますが、ヤーマは3時間、ダンダは先ほどのガティカと同じ24分とのことなので、8ダンダは192分(3時間12分)です。3時間息を止める……。
プラティヤーハーラは、ヨーガスートラの時代からヨーガの修行の段階として挙げられていた「感覚制御」を意味するものですが、内外からの刺激に心乱されないようにせよ…というだけで、そのための具体的な行法などは他の教典では示されていませんでした。
参考:ヨーガスートラ解説 2.54-2.55 〜プラティヤーハーラ(制感・感覚抑止)〜
シヴァサンヒターでは、ここで「クンバカを長くしていくことが、プラティヤーハーラを深める」という具体的な道を示しています。
また、もうひとつのプラティヤーハーラのヒントとして、以下のことを示しています。
3.68節「えらいヨーギーは、どんなものを知覚しても、それらをすべてアートマンとして思念すべし。どのような感官によって知覚しても、上記の如き処置方法を知る人はその感官を克服することができる。」
この世界で知覚できるすべてのものは、アートマン(真我)である自分自身が作り出したもの(あるいは自分そのもの)である、というように考えると、感覚によって心を乱されることがなくなります。
パリチャヤ段階
パリチャヤ段階で起こること
3.71節「〔パリチァヤ段階〕さらに調気の修行を続けてゆくと、ヨーギーはパリチァヤの境地に達する。この境地においては、気は月と日の気道を捨てて、不動な状態にとどまる。」
3.72節「そうして積み重ねられた気は体内の活動能力を摂取し、種々のチァクラを貫いて、スシュムナー気道の空洞の中を決然と登ってゆくのである。」
左右の気道(イダー・ピンガラー)が整った後、心が不動になって中央の気道(スシュムナー)が通るようになります。やはり基本の片鼻呼吸法が重要となりそうです。
3.72節で佐保田訳を読むと、ここで言う「気」はクンダリニーのことか?と思ってヴァス訳とマリンソン訳を見てみると、やはり「シャクティ(クンダリニー)がチャクラを貫いてスシュムナーを登っていく」という説明がありました。プラーナとクンダリニーは、どちらも微細な力のため「気」とまとめられてしまいがちですが、これらは全く別の力です。
パリチャヤ段階における行法
業(カルマ)を滅する行法
パリチャヤ段階に入ると、業(カルマ)の3元素(サットヴァ・ラジャス・タマス)を直観するようになるといいます。これらはヨーガスートラでも物質世界を作る素である3つのグナとして出てきます。
用語:グナ guṇa
その業を滅するための行法として、再び「聖音オーム」を用いるべしと説明されています。
また、業を滅するために「カーヤヴューハ」の行法を行うべしと指示されています。これは、過去の業によって来世以降に生じるべく定められている体を一気に作ってしまい、すべての体に入って業の果報の経験をし尽くすというものです。
五大元素への集中(パンチャ・ダーラナー・ムドラー)
業を滅する行法を行った後、五つの様式のダーラナー(凝念・集中)を行うべしと指示されています。ダーラナーは、8支則のヨーガでもプラティヤーハーラの後に来る段階です。
五つの様式とは、ここでは具体的に指示されていませんが、五大元素それぞれに対して集中するもので、ゲーランダサンヒター3.68節以降でパンチャ・ダーラナー・ムドラーとして詳しく示されています。パンチャは「5」の意味です。
参考:ゲーランダサンヒター概説3.68-3.81 〜ムドラー解説4〜
各チャクラへの集中
各チャクラへのダーラナー(集中)の行法も指示されています。ただ、ここは訳者によって解釈が異なり、研究が必要な部分があるかもしれません。
佐保田訳とヴァス訳では、5ガティカ(120分)の間ずつ、基底、性器、ヘソ、心臓、喉、眉間に集中することで、五大元素による害はなくなると説明されています。これらは6つのチャクラの位置にあたります。
マリンソン訳では少し解釈が異なっているようで、ヘソと心臓のかわりに、「性器の上」と「ヘソと心臓の間のエリア」(太陽神経叢?)があり、「喉」については含まれておらず、集中するべき部分は合計6つではなく5つになっていました。佐保田氏が「喉」と解釈していたmadhyakeという言葉が、どうも「真ん中」「中心」を意味する言葉のようです。ヴァス氏も「throat(Vishuddha)」と訳していますが、「喉」の言葉がどこから出てきたのかははっきりしないようです。五大元素との関係性を考えると、集中するエリアも5つとなっていることはあり得るかもしれません。
ニシュパティ段階
3.79節「〔ニシュパティ段階〕その後修習を積むにつれて、ヨーギーにはニシュパティ(完成)の境地が生ずる。それによって、無始の過去からの業の種子を超克して、不死の甘露を飲むことができる。」
3.80-81節「それは、現生に解脱して心が寂静に帰したヨーギーが自己の努力によって三昧の完成に到達した時、また自らの希望通りに三昧の完成を得た時に、ダイナミックな気は知能と行動力とを抑えこみ、すべてのチァクラを制圧して、すみやかに英智のなかに没入する。」
最後のニシュパティ段階について、3.79節の内容は訳者によってほぼ共通していますが、佐保田訳3.80-81節の内容は、訳者によって重要な違いがありそうです。(ちなみにこの章でも節の数え方は訳者によってかなり異なっています。ヴァス訳では3.67節、マリンソン訳では3.78節にあたります。)
ヴァス訳では、以下のようになっています。
When the jivan-mukta (delivered in the present life,) tranquil Yogi has obtained, through practice, the consummation of samâdhi (meditation), and when this state of consummated samâdhi can be voluntarily evoked, then let the Yogi take hold of the chetanâ (conscious intelligence), together with the air, and with the force of (kriyâ-sakti)
conquer the six wheels, and absorb it in the force called jñâna-sakti.翻訳:静穏なヨーギーが、ジーヴァン・ムクタ(現生解脱)によって修行を通じてサマーディ(瞑想)の完成に達し、この完成したサマーディの状態を自発的に呼び起こすことができるようになったとき、ヨギはチェータナー(意識的な知性)を気とともに掴み、クリヤー・シャクティの力で六つの輪を征服し、それをジュニャーナ・シャクティと呼ばれる力に吸収する。
マリンソン訳では、以下のようになっています。
When samadhi automatically arises together with nishpatti, the impetuous breath takes hold of consciousness and the action shakti, hurries through all the chakras, and comes to rest in the knowledge shakti.
翻訳:サマーディがニシュパティと共に自然に生じると、衝動的な呼吸は意識と行為のシャクティを捕らえ、すべてのチャクラを駆け抜け、知識のシャクティに落ち着く。
佐保田訳ではシャクティと言わず「ダイナミックな気」としていますが、原文ではクリヤー(行為)とジュニャーナ(智慧)の2つのシャクティについて述べられているようです。
用語:シャクティ śakti
現代のクンダリニーヨーガでも、骨盤底のクンダリニー・シャクティが覚醒してスシュムナーを駆け上がり、各チャクラを通りながら賦活していくという原理が用いられることが多いですが、シヴァサンヒターのこの部分では、気が整った最終段階に到達するとサマーディとともにその現象が「自発的に」起こる様子を説明しているようです。
シヴァ派の定義ではシャクティは以下の5つの形態があり、この順番で前のシャクティから次のシャクティが現れていくといいます。
- パラ(パラマ)・シャクティ
- アーディ・シャクティ
- イッチャ・シャクティ
- ジュニャーナ・シャクティ
- クリヤー・シャクティ
シャクティとは創造力であり、世界の創造にはこの順番でそれぞれの力が働いていったとされます。パラシャクティ(最高のシャクティ)はシヴァ神自身から発せられるといいます。アーディは始まりの力、イッチャは意志の力、ジュニャーナは智慧の力、クリヤーは行為の力です。
シヴァサンヒターで説明されている内容によれば、クリヤー・シャクティが各チャクラを征服して、ジュニャーナ・シャクティに還っていく様子が読み取れます。これによって上記の順番の逆向きに進んだことになるので、物質世界の束縛から一歩脱して根源の方へ近づいたということになります。
シャクティの捉え方は、イッチャ・ジュニャーナ・クリヤーの3つを掲げる宗派もあり、ひとつひとつ担当する神を定義するなど、様々な解釈があります。同じ名前なのに位置づけが異なったりするのがややこしいところです(最高神とする神が異なっていたり)。このあたりも研究していく余地のあるところかと思いますが、宗教文化研究の範疇になってくるので、いったんハタヨーガ・クンダリニーヨーガ研究としての概説としてはこのくらいにしておきます。
このあと、ムドラーやアーサナ(坐法)などの具体的な行法の話に入っていきます。
次記事:シヴァサンヒター概説【9】3.82-3.97 気の操作(ケーチャリームドラー・カーキームドラー)
前記事:シヴァサンヒター概説【7】3.35-3.47 ヨーガ修行の禁戒・勧戒と生活リズム